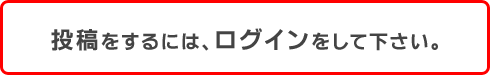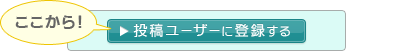大凧あげ祭りは江戸川河川敷で、毎年5月の3日と5日に開催される伝統ある行事です。 大凧を揚げるのは百数十人。見物客は10万人以上。江戸川河川敷を埋めた人々が見守る中、大凧が空へ舞い揚がります。その隣では、小凧や小町凧、企業名入りのコマーシャル凧などが舞い、お祭り気分をさらに盛り上げます。子どもたちの健やかな成長を願い市民一体で開催される祭りです。 かなり歴史のあるイベントで始まりは江戸時代後期の天保12年(1841年)、生国出羽国山本郡水沢邑 (しょうごくでわのくにやまもとごおりみずさわむら)の西光寺の弟子、浄信という僧が、各地巡礼の折に宝珠花 (ほうしゅばな)の小流寺に宿泊した時に、その土地の人々を集め養蚕の豊作占いとして凧揚げの話をしました。「繭の値段が上がる」と「凧があがる」の意味を掛けていると言われています。その占いを聞いて人々は、数十個の凧をあげて繭の豊作を占うというようになったと伝えられています。 今では繭の収穫前ににぎやかに揚げられた凧を旧暦5月の端午の節句に周辺の男子出生のお祝いとして、各戸では子どもの名前、紋章を書いた大凧、小凧を作って、凧あげ祭りをしています。 大凧の前で「健康祈願のおはらい」を受けます。「名入りの手作り凧(54センチメートル×40センチメートル)」を受け取り、大凧の前で記念撮影をするイベントになっており、初節句に参加した「子どもたちの名前を書いた紙」を大凧に貼り、午後2時ごろに「健康と幸福な成長を願って」大空に舞い上げられます。その凧はかなり巨大で、大凧は縦15メートル、横11メートル、重さ800キログラム、小凧は縦6メートル、横4メートル、重さ150キログラムと、かなりの迫力がありました。こんな大きな凧が上がるのかと思いましたが、上手く飛ばしていてビックリしました! 初節句を迎えるお子さんを毎年募集していて、申し込みなど詳細は、毎年1月ごろとなっております。