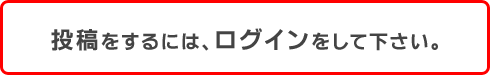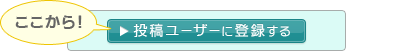毎年4月14日、15日に行われる八幡まつりは1000年以上の歴史があるまつりです。始まりは西暦275年に近江を訪れた応神天皇が、現在の日牟禮八幡宮へ参拝される際に、琵琶湖湖岸の南津田にある7軒の家が松明(たいまつ)を作り、火を灯して道案内をしたのではないかと伝えられています。 八幡山城城主であった豊臣秀次が八幡町を開町する前からある、旧村落十二郷の氏子によって行われています。14日は宵宮祭と呼ばれ、各郷のヨシと菜種ガラを材料にした松明が奉納され、その松明を奉火するもので、10メートルの大きさを超える松明もあります。14日の朝には上ノ郷と下ノ郷の代表者によって笹竹を材料にした大松明結いが日牟禮八幡宮の境内にて行われます。夜は大太鼓と鉦をならしながら各郷が宮入りをし、打ち上げ花火を合図に古来の順序により次々と松明に奉火します。引きずり松明やとっくり松明、振り松明、船松明などさまざまな松明もあり、壮大な火柱となりそのスケールは圧倒的です。 15日の本祭、大太鼓まつりでは各郷を大太鼓を担ぎ練り歩き、日牟禮八幡宮の桜門を目指します。夕方ごろから宮入りをして、拝殿の前で大太鼓を差し上げ、神職や神役などからの祝詞を受けます。大太鼓の振動がカラダの芯まで響き渡り、大太鼓を若衆が担ぐ姿が印象的です。 実は私の住んでいる町が旧村落十二郷の下ノ郷にあたり、子どものときから父が大太鼓を担ぎ、叩く姿を見てきました。いつか自分も歴史あるこの八幡まつりに参加したいと、ずっと思っていました。大人になり実際に参加してみると、松明結いの大変さ、太鼓を組み立てる大変さを知りました。初めて見る結び方や初めて聞く言葉がたくさんあり、その言葉を使い器用に結んでいる父や近所のおっちゃんをとてもかっこよく感じました。 まつり当日は屋台や出店もあり、子どものときはそれを目当てでお小遣いをもらい、友達や家族と行っていたことも思い出します。